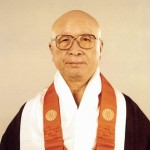大正大学 仏教学科で、毎年春学期・秋学期一回づつゲスト講師として招聘を受け、今年で3年目になりました。
6月1日、受講生は28名です。授業のはじめに、大正大学の卒業生でいらっしゃる草津栄晋教務部長様がご挨拶されました。
「大覚寺は真言宗大覚寺派の本山です。1200年の歴史があり、もと嵯峨天皇の御所だったところ。その御所で発祥したのが嵯峨御流です。当初はまだ嵯峨御流という名前ではありません、後になって名前が誕生したのです。日本の公的な記録の中では、類聚国史という書物の中に、嵯峨天皇がお花をいけられたという記録が残っております。それは、まだ嵯峨天皇様が皇太帝の時に、お兄様の平城天皇の御見舞いのために、神泉苑でお花をいけられたというもので、すなわち、嵯峨天皇様はお花を実際においけになられた方だ、という確証がある御方なのです。この嵯峨天皇様が、当時嵯峨御所とよばれていた大覚寺でお花をいけられたという寺伝が私ども嵯峨御流の発祥になっています。嵯峨御流は、密教的な思想体系をもった世界で唯一の華道であるといえます。
いけばなの中に、密教の六大思想というものが反映された花型(荘厳華)があり、それぞれの役枝に六大を形にして表現しています。後程(実演で)見て頂けると思いますが、きちんとした歴史的な伝統あるいけばなです。今日は、生活の中にあるいけばな、その中にも仏教や密教的なものの薫りが伝えられていることを感じて頂ければ幸いです。」(要約)続いて私の講義テーマ「いけばなで命と自然の大切さを学ぶ」について、パワーポイントを使いながら、実演を交えて約1時間お話ししました。嵯峨御流の花態にはすべて曼荼羅の宇宙観が現れています。景色いけにおいては、命の根源である水の流れの連続性が風景を生み出すという発想で、山から海までの「七景」をつなぐと、一つの大景観が表現できるというところが、嵯峨御流の独自性です。景色いけが出来た昭和6年頃の日本の時代背景なども説明しながら「景色いけ・七景の水の取り方」の中から「深山の景」「沼沢の景」「河川の景」をデモンストレーションで紹介し、「いけばな」は生命感の表現であると説明しました。
また、新型荘厳花器「そわか」を用いて荘厳華をいけ、曼荼羅の宇宙観である六大無礙の思想を、森羅万象を表す「地・水・火・風・空」の5つの役枝と精神性を表す「識」の6つの要素の調和美で表現すると説明しました。

前期を5月22日に拝見し、本日25日は後期最終日を拝見してきました。朝、10時過ぎに会場であるそごう広島店9階に到着しましたが、入場者は長蛇の列で、昨日は入場制限されていたそうです。
後期、嵯峨御流からは、8花席に12名が出瓶されていました。写真を掲載させていただきます。
後期の5人合作席の作品のモチーフは、「平和の灯」。戦後70年に因んで、世界平和を願う作品とされました。
広島市に建てられている、「平和の灯」の姿を基に、その手首を合わせて、手のひらを大空にひろげた形をいけばなに取り入れられたそうです。
役員席 吉田泰巳先生
一人席 元中裕甫先生 那須真澄先生 大枝美紀甫先生 三浦良楓先生
沖田信甫先生 唐川幸治先生
五人席 石田恒甫先生 青野直甫先生 尾熊千鶴子先生 益本明甫先生 大和亭甫先生
愛宕神社の愛宕神・野宮神社の野々宮神をお祭りする嵯峨祭りは450年以上の歴史があり1537年の文献に記述が見られる古いお祭りです。祭神が二社、神輿も二基ある事や、お祭りの主催が江戸時代まで大覚寺・清涼寺(棲霞寺)などのお寺だということが他と違う特徴なのです。
二基のお神輿は清涼寺の前を通り大覚寺に到着し、そこで儀式が行われます。大覚寺勅使門を五基の剣鉾がくぐり抜け、神輿の担ぎ手と2基の神輿は勅使門の前で大覚寺僧侶の読経と神社の祝詞の両方、神仏習合の形で清払いをお受けになります。大覚寺を出た後は、五基の剣鉾(オモダカ、リュウ、キリン、キク、ボタン)が「りん」をならし、神輿が通る為に邪気を払いながら一日かけて嵯峨一帯を練り歩くのです。
毎年、第四日曜日。お旅所出発は10時。大覚寺到着は11時50分。町内を練り歩いてお旅所へ戻るのは17時。
お祭りの法被には、大覚寺の寺章「嵯峨」の山山を上下に重ねたものがつけられています。
一青窈さんが歌う「女ひとり」。NHK テレビ、大覚寺から生中継されました。宸殿と
2015年4月28日、NHKテレビ20時から約1時間放映された「歌謡コンサート」の中で、大覚寺から生中継が行われました。大覚寺の重要文化財「宸殿」の牡丹の障壁画の間には、いけばな嵯峨御流の大振りな作品がいけられ、その前で、一青窈さんが「女ひとり」を3番まで歌われました。
3番の歌詞は、「京都嵐山大覚寺・・」まさしく大覚寺がテーマになっています。映像では、宸殿の檜皮葺の屋根を鳥瞰撮影し、一青窈さんが真っ白なドレスをひるがえしながら村雨の廊下から宸殿へと入ってこられる様子がうつされていて、ライトに浮かぶ御所風の佇まいは息をのむほどに美しく感じました。
撮影の前日に宸殿前の白州に建てられた3階建てほどの高さのある櫓は、このアングルを撮影するのに必要だったのか、と納得しました。写真は、宸殿にいけられた 5つのいけばな作品のスナップです。6名でいけこみをし
ました。
曲の前の、アナウンサーと一青窈さんの生中継での会話:
アナウンサー「京都の西に位置する大覚寺。観光名所として人気の嵐山の近くに位置していて、歴史は、平安時代にさかのぼります。この大覚寺のもう一つの魅力をご紹介したいとおもいます、こちらをご覧ください、それは、いけばななんですね。およそ1200年の歴史を持つ、いけばな嵯峨御流の総司所、いわゆる家元なんですね。今日
のために特別にいけて頂いたのです。
一青窈さんは、「この大振りのお花が大覚寺にピッタリですね」と仰っていました。
嵯峨御流Washington D.C.支部長 Bruce Wilson先生が嵯峨御流の勉強の為来日されました。
 Wilson先生は、毎年大覚寺に半月ほど参篭して、毎日嵯峨御流のレッスンをうけておられ、今年で9年目になります。先生はアメリカ・メリーランド州にあるセントメリーズカレッジの教授で、大学の授業の中でも嵯峨御流を教えていらっしゃいます。
Wilson先生は、毎年大覚寺に半月ほど参篭して、毎日嵯峨御流のレッスンをうけておられ、今年で9年目になります。先生はアメリカ・メリーランド州にあるセントメリーズカレッジの教授で、大学の授業の中でも嵯峨御流を教えていらっしゃいます。
今年9月から、いけばなインターナショナルWashington D.C.支部の支部長に就任されることが決まっており、益々ご活躍の先生の熱い授業風景をスナップしました。5月28日まで大覚寺に参篭される予定です。
BS-TBS 高島礼子・日本の古都~その絶景に歴史あり~6月10日(水)22:00~22:54この番組で、大覚寺狩野派の障壁画が取材されました。私は嵯峨御流のお話しを少しさせていただいています。ぜひご覧くださいませ
高島礼子さんが、狩野派の障壁画を訪ねる番組の取材があり、大覚寺大玄関供待にいけてある作品の前で、いけばな嵯峨御流のご説明を少しさせていただきました。
5月20日から25日まで、広島市そごう百貨店で開催される、日本いけばな芸術協会主催の中国地区展を22日に拝見してきました。
22日は前期の会期中で、嵯峨御流からは、7花席に11名が出瓶されていました。写真を掲載させていただきます。
5人席の「十二律管」の作品は、迫力ある満天星躑躅(どうだんつつじ)を主花材として、風を感じる大作でした。来場者の方から、雅な雰囲気ですね、とのお声がたくさんあったそうです。
一人席
黒田祥甫先生 唐川幸洲先生 廣野薫甫先生
粟田一甫先生 石井美智甫先生 重田清風先生
五人席
服部精村執行長様、光岡道寛先生、戸田華園先生、森脇恵伊甫先生、谷口兼甫先生
5月17日。大覚寺第60世門跡、片山宥雄大僧正猊下のお通夜式に、お参りさせていただきました。
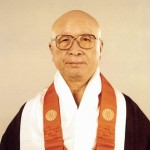 大覚寺第60世門跡、片山宥雄大僧正猊下が遷化され、御自坊の明王院様に於いて行われた5月17日のお通夜式にお参りさせて頂きました。
大覚寺第60世門跡、片山宥雄大僧正猊下が遷化され、御自坊の明王院様に於いて行われた5月17日のお通夜式にお参りさせて頂きました。
片山大僧正猊下は享年96歳、平成9年に大覚寺門跡・嵯峨御流華道名誉総裁にご就
任、平成16年に真言宗長者を務められました。
広島県福山市、明王院名誉住職。
心からご冥福をお祈り申し上げます。
横浜司所は、35周年を迎え、5月16・17の両日、記念華展を「みなとみらいギャラリー」で開催されました。テーマ『花意竹情』に因み、琳派の絵画を連想させる青竹をふんだんに用いた設え。モダンなギャラリーの隅々まで上手く使いこなされた会場構成でした。
 |  |
| 司所長 大用裕甫先生 | 御題「本」の花器を活用されています |
 |  |
| 会場風景の一部 | 通路の工夫 |
 |  |
| 会場風景 | (向かって右より) 前司所長長瀬節甫先生・ 前々司所長真坂牧甫先生 ・いけばなインターナショナル鎌倉支部 前支部長長崎登世様 |
 EPSON MFP image |
5月17日、御室仁和寺で開催された第99回流祖奉献全国挿花大会を拝見に伺いました。立部祐道門跡猊下にご挨拶申し上げ、その後門跡猊下が寺内の作品をご巡覧なさるのを、ご一緒させていただきました。
家元、立部祐道門跡猊下の作品 門跡猊下、華務長小田美風先生と。
小田美風華務長様と。 先の華務長川辺宏雄先生・
本能寺未生流華務長中野恭心先生と。