華道二葉流の華展を拝見しました。
6月4日、5日の両日二葉流家元華展が、あべのハルカスのある近鉄アート館で開催され、5日に拝見させていただきました。
華展のテーマは「妙趣清宴」。いけばなと南宗盛物を堪能させていただき、五代目堀口昌洸家元ご夫妻と、お嬢様の桂邦先生にもご挨拶できました。
 | |
 |  |
HOME > 華務長の部屋

Profile
辻󠄀井ミカ先生は、祖父・父の跡を継ぎ昭和43年より嵯峨御流に入門され、平成2年派遣講師となり本格的に華道家としての活動を開始される。
平成8年華道芸術学院教授に任命されたのを始め、華道評議員、華道理事、華道企画推進室副室長等の総司所役職を歴任、平成16年より平成26年3月まで弘友会司所の司所長に就任される。
そして平成26年4月1日より華道総司所華務長に就任。
現在、日本いけばな芸術協会常任理事、大正大学客員教授を務められる。
6月4日、5日の両日二葉流家元華展が、あべのハルカスのある近鉄アート館で開催され、5日に拝見させていただきました。
華展のテーマは「妙趣清宴」。いけばなと南宗盛物を堪能させていただき、五代目堀口昌洸家元ご夫妻と、お嬢様の桂邦先生にもご挨拶できました。
 | |
 |  |
6月6日は、いけばなの日。昔からお稽古はじめは6月6日、とされてきた事に因んで全関西のいけばな界で連携し、提唱しているものです。
京都いけばな協会では、6月4日、5日の両日、京都いけばなプレゼンテーション2016<伝統と現代 花会>のテーマのもと、華展やいけばな体験、またアーティストトークとして華道家のお話など、濃い内容の催しが開催され、留学生などで賑わっていました。
華展に出瓶されていた嵯峨御流の3作品をご紹介します。
嵯峨御流会とは、次の目的で平成15年に発足した会です。
https://www.sagagoryu.gr.jp/sagagoryukai/
* 嵯峨御流の精神と伝統を守り、「今」に活かすとともに、 「未来」へ生き生きと継承すべく、平成15年に発足しました。
* 総司所と連携し、全国ネットで相互の親睦を図りつつ、自己の研鑚と嵯峨御流いけばな文化の高揚に努めることを目指します。
* 会員各自の向上心、独自性をさらに引き上げるべく、会員の声を生かし、会員の皆さまに喜んで参加していただける活動を推進します。
平成28年度の総会が5月21日に開催され、そのご報告記事を会長からいただきましたので、ご紹介いたします。私は、残念ながら所用の為、出席できませんでした。
「平成28年度の総会を5月21日(土)、大覚寺の華道芸術学院に於いて開催いたしました。 午前中は、、御来賓の久保洋巳華道課長様のご挨拶を頂戴した後、全国から集まった会員によって熱心に議案が審議され、それぞれ承認可決いたしました。 役員選出では会長に宮本登美甫氏が再任されました。 午後からの講師に和歌の家元・冷泉家第25代当主、冷泉為人先生をお迎えしました。 講演に先立ち黒沢全紹 門跡猊下と御歓談をされ、その後「日本人の自然観」と題した記念講演を賜りました。 スライドを交えての奥深いお話に一同魅了され、有意義な一日となりました。 嵯峨御流会 宮本登美甫」
 |  |
 |  |
 |  |
大覚寺大沢池に、「名古曽」蓮の浮葉が出だしました。ヒシも沢山出てきています。
7月30日は、華道総司所主催の「遊花一日 夏期大学」が行われ、受講者の方に観蓮節(象鼻杯)をお楽しみ頂く事になっていますので、今年も元気に開花してくれるよう祈っています。
象鼻杯とは、蓮の葉に酒を注ぎ、その酒を、長い茎の先端から飲む、その様子が象の鼻のようであることから名づけられたもの。とても優雅な楽しみと言えます。接待役は、千早の装束を付けた嵯峨御流会の先生方です。
遊花一日夏期大学では、京都嵯峨芸術大学の多田千明先生を講師にお招きして、「造形美と IKEBANA」と題して、多田先生の作品にいけばなとの出会いをライブのような形で、楽しんで頂くつもりです。
また、午後からは、受講生の皆様が花器や花留を創作し、花を関わらせるチャレンジをして頂きます。
詳細は嵯峨御流ホームページの「お知らせ」をご覧下さいませ。
 |
古流松涛会の90周年華展を拝見し、会場で、お家元榎本理福先生にご挨拶させていただきました。
作品お写真を撮らせて頂きましたのでご紹介いたします。
 |  |
 |  |
 | 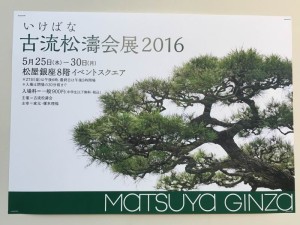 |
雲一つない晴れやかな日となった平成28年5月29日(日)、東北・関東地区連絡協議会主催「いけばな公開講座『華やかな平安文化の薫りをいける』」が、東京都内のコクヨホールにおいて開催されました。
関東地区8司所(東京司所、埼玉司所、神奈川司所、東都司所、横浜司所、東京公友会司所、東京御流司所、信州司所)及び東北地区3司所(秋田司所、山形司所、仙台司所)からの受講生で、会場は満員でした。
開演に先立って、大覚寺執行 草津栄晋部長様から 大覚寺カフェについてのお話しがあり、大覚寺カフェの素敵なホームページの映像の一部を、プロジェクターで皆様にご紹介されました。その後、開講ご挨拶が大用裕甫関東地区連絡協議会運営委員長からありました。
公開講座 第一部の私の50分の講演は、「いけばなで美しい地球を守る」。
続いて、服部孝月華道企画推進室長と私で、深山の景・城ケ崎海岸の海浜の景をいけました。
第二部の50分間は、デモンストレーション。テーマは「花まんだら」。服部先生と 私で。地、水、火、風、空の五大森羅万象をいけばなで表現しました。
地:「深山の景」・・・貝塚伊吹・古木・夏櫨・躑躅・小菊・岩
水:「荒磯の景 城ヶ崎海岸の風景」・・・溶岩・岩・松
火:青銅「爵」花器に、炎のイメージで。・・・炭、楓、煙の木、ヘリコニア、美人蕉、グロリオサ、金着色芭蕉の葉
風:嵯峨好み「四方」に、芭蕉の生花。
空:「亀甲」の花器を用いて、荘厳華。・・・パンパス、松、ビャクシン、サツキ、紫陽花、アンスリウム、他
閉会のご挨拶は、伊藤竜甫東北地区連絡協議会運営委員長でした。
森羅万象をテーマにいけた舞台の花が発する響きが、見て頂いた受講生の方の心に伝わり、会場全体が一つの大きな熱気に包まれたように感じ ました。
ご協力いただいた東北・関東地区の先生方に感謝、舞台の助手をしていただいた研究生の方々に感謝、そして舞台の花を一心に見つめて下さった皆様にも心から感謝申し上げます。
 | |
 | |
 |  |
 |  |
 |  |
5月22日、奈良市にて、草月流の岩本知星先生が社中展を開催され、拝見させて頂きました。場所は、ならまち 菓子司「中西与三郎」。
大正年間に建てられたお菓子屋さんで、130年の重厚な建物に、当代の社長さんが和モダンなセンスで手を入れられている、素敵な空間。この場に、岩本先生とお社中さん方の、繊細かつパワフルな花が濃密に関わり、建物は異空間の輝きを放っていました。
すべての作品をご紹介したいのですが、ごく一部のスナップを掲載させて頂きます。
 |  |
 |  |
 | |
 |  |
<花を通じての友好>をモットーに、世界60ヶ国164支部をもつ公益社団法人いけばなインターナショナルの、大阪支部創立25周年目のフェスティバルが、5月22日(日)10:00から16:30まで、大阪国際交流センター2階会場で開催されました。会長は岸上昌子様。
フェスティバルでは、メンバーによる華展と、在阪各国総領事館のいけばな作品が展示されました。10:30から開会式が行われ、外務省から関西担当大使 三輪昭様、I.I.会長片野順子様、I.I.世界大会委員長のご挨拶。ご来賓には、在阪各国総領事やご夫人などがお見えになりました。続いて能「高砂」山本章弘様。12:00から14:00までは、留学生対象のいけばなワークショップ。嵯峨御流から、私も含めて多数の会員が作品を展示し、ワークショップにも、嵯峨御流が参加協力いたしました。
楽しいバザーも開催され、「約1000名の来場者に、いけばなに親しんで頂けました」と、I.I.大阪支部フェスティバルコーディネーターで元会長の高林みどり様から大阪日々新聞に掲載された記事を送っていただきましたので、併せてご紹介します。
5月21日・22日の両日、京都文化博物館において開催された華展を、22日に拝見致しました。テーマは、「花咲き花咲く(はなさき、はなわらう)」。
会場では、華やかな御所車が雅に飾られ、伝承花や心粧華など、いずれも会員の皆様の熱意にあふれた力作が展示されました。京都のほぼ真ん中に位置する会場には、一般の方も訪れられて、終日ご盛会でした。
 |  |
 | |
 | |
 | |
 |
5月17日、真言宗大覚寺派青年教師会総会に於いて、ご挨拶をさせていただきました。その内容の一部と、その際の、私の想いを書かせていただきます。
平成27年度に、嵯峨御流は、荘厳華の新型花器「そわか」を考案し、全国109司所で特別講習会「荘厳華へのいざない」を開催致しました。
ところで、荘厳華は、昭和23年に嵯峨御流の花態として確立されたものですが、近年の生活環境に合わせて、もっと身近に祈りの心を託す花をいけられるようにと、いけばなの執行部が長年かけて研究し発表したのが、新型荘厳華器「そわか」です。
さて、この「そわか」を用いた「荘厳華へのいざない」講習会では、実技の前に荘厳華の基本理念である六大の理念と、曼荼羅の講演を、青年教師の僧侶の方にしていただきました。深淵な理念をいけばなの研究生にもわかりやすく、興味を引くようご説明頂いたことで、受講者からは、心に響きました!感激しました!という声が総司所に沢山届けられました。
青年教師という、お若い僧侶の方々の凜としたお姿や、所作、熱いお話振りが、研究生の心に感動の響きとなって伝わったのだと思います。 青年教師会の中から17名の方々が日々のお忙しい法務の中、いけばな研究生の為にお時間をさいてご奉仕し、講演をして下さり、嵯峨御流全国109司所のそれぞれの研究会会場まで足を運んでくださいました事に、深く感謝申し上げます。今回の「荘厳華へのいざない」特別講習会で、研究生は、いけばなと仏教の関わりについて学んだのみならず、伝える姿勢や常に原点に立ち返る姿勢の大切さを、参加した全員が感じ、学ばせていただきました。さらに、今の社会の中で、いけばなを伝える意義についても学びとり、それぞれの人が心の中に核となる信念を持つ事が出来たと思います。いけばなは、植物と触れ合って命を感じる事や、日々変化する花に愛おしさを感じる事によって美しくいける事ができます。また、嵯峨御流のいけばなには、花即宗教という信念が基本にあり、命の営みを花で表現できるのも、本流の魅力です。> 大きな意味で人々に命の大切さと平和を願う心を広げる事が、これからの私ども華道家にとって大事な使命だと思いました。